毎月1回、ゲストとDC研究会のメンバーが語り合う「DCオンラインゼミ」。今回は公立小学校の教員である、鍋谷正尉先生にご登壇いただき、クラウドを活用した自身の教育データの管理と、それに関連した教育委員会との連携に関する情報をご提供いただきました。
今後、動画のアーカイブを有償で配信することも検討しております。以下の概要を読んで興味が出てきたという方は、JDiCE事務局までご相談ください。
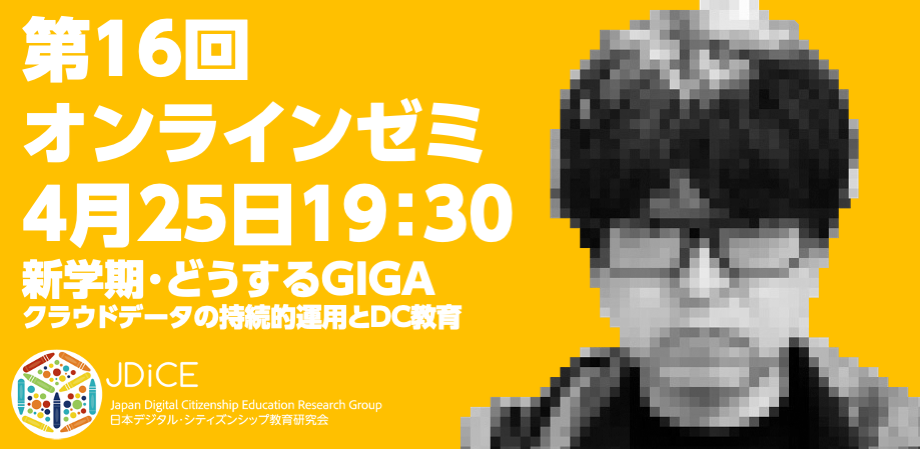
今後のDCオンラインゼミを受講されたい方は、研究会のイベント予約サイト(無料)であるPeatixをぜひフォローください。
卒業生のデータ移行に関する実践
渋谷区立の小学校の教員である鍋谷先生は、小学校の卒業生が中学校へ進学する際のクラウドデータの引き継ぎに関する実践を報告しました。特に、区立中学校以外へ進学する児童生徒に対して、Microsoft 365のOneDriveに保存されたデータを外部ストレージサービスを用いて持ち出す仕組みを整備した経緯や工夫について詳述しました。鍋谷先生は、この取り組みが児童自身が自分のデータに責任を持ち、大切に扱う意識を高めるきっかけとなったことを強調しました。また、渋谷区教育委員会が適切かつ迅速に対応し、学校現場への負担を最小限に抑えたことについても言及されました。
データ管理の課題と教育的意義に関する議論
鍋谷先生の発表を受け、参加者間ではデータ管理における個人情報や著作権の問題について深い議論が行われました。データを持ち出す際の責任の所在や、他者の著作物を含むデータの取り扱いについて、法的かつ教育的な視点から検討が進められました。参加者からは、児童生徒がデータに対する愛着や責任感を持つことの重要性が指摘され、教師自身もクリエイターとしての意識を高める必要性が共有されました。さらに、このような教育実践がデジタル・シティズンシップ教育の重要な要素であり、今後の教育モデルとして広がる可能性があるとの見解が示されました。
教育的意義と今後の展望
議論を通じて、児童生徒が自分のデータに対する愛着を持つことや、教師自身もクリエイターとして意識を高めることが、デジタルシチズンシップ教育において重要な要素であることが再確認されました。また、このような取り組みが、児童生徒が自身のデータを主体的に管理し責任を持つ態度を育てる機会となることから、今後全国的な教育モデルとしても展開できる可能性について、後半のディスカションパートでは登壇者メンバーからもさまざまな意見がだされました。
